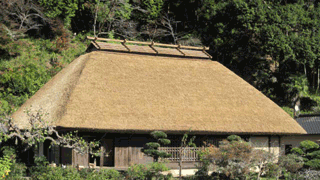儒教
仏教と同様、日本に入ってきてから日本化され、独特の日本儒教となった。
儒教は先祖の魂は不滅であるとする信仰(先祖崇拝)と、善行も悪行もそのまま返ってくるという信仰(天神相関説)の、二つの宗教概念をベースとした宗教である。
孔子は「怪力乱神」を否定したが、先祖の魂が不滅で永遠に子孫を見守っているというのは、怪力乱神を認めていることであり矛盾している。しかしこれは証明しようのない宗教的問題である。儒教は宗教なのである。
位牌のルーツは儒教である。孔子が儒教として理論建てる以前、儒者と呼ばれた人達は葬儀屋であり、儒礼に基づいて執り行っていた。彼らは「死者の魂は不滅でご先祖様として我々を見守っていてくれる」と考えていたので、死者の象徴として位牌(木主)を立てた。しかし仏教では魂は不滅でも死ぬと輪廻転生して別のものに生まれ変わり、記憶も失くしてしまうと考えたため、本来位牌は用いない。ところが日本神道では「神の依代(よりしろ)」という考えがあり、これが位牌に相当するものとして日本の仏教に取り込まれたらしい。
儒教では子孫を絶やしてはならない。先祖を祭る者がいなくなるからだ。ただし子孫は男系のDNAを受け継ぐ者でなければならないとされ、妻に男子ができなければ他の女性と関係を持って男子を作ることが善とされる。養子を取る場合には、日本ではどこから縁組みしても良いが、中国や朝鮮では男系の血が繋がっている所から縁組みしなければならない。だから必ず同姓ということになる。
儒教の第一義「孝」をテーマにした物語集「二十四孝」を読んだ魯迅は、近代化を阻む悪しき思想だとして否定した。
儒教の徳目「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」の内「仁」は特別で、他の七つを修めることでようやく得られる最高の理想的人格であるとする。
日本は明治以降近代化のために西洋思想を取り入れたが、道徳のバックボーンを形成するために、神道を仏教と切り離して国家神道とし、ローマ法王に対抗すべく天皇をトップに祭り上げた。また天皇への忠義を強いるため儒教を用い、国民は天皇の赤子であるとして忠・孝を一致させた。
■儒教の問題点
- 平等主義にならないこと。人間関係の濃さの違いが根強くあるために、なかなか物事を変えられない。
- 尚古主義であること。何でも昔の方が良かったとするので、強い保守主義となり物事を新しく変えることができない。
- 商売を悪とするため経済的視点がない。
- 科学的視点がない。
経済という言葉は日本人が作ったもの。他に権利・哲学・科学・鉄鋼などがあるが、日本へやって来た留学生によって中国や朝鮮で使われるようになった。
日本独自の「和」の思想は、儒教と仏教の毒に対するカウンターパンチである。
日本は科挙を取り入れなかった。その理由は「和」の思想が競争を嫌ったからである。また、試験が儒教に限定されていたことにもある。儒教に限定されていたのは、最も徳のある(はずの)皇帝を補佐するのだから、一般民衆の中で最も徳のある者を選び出すというのがその理由であった。だから儒教の聖典「四書五経」の理解度をペーパーテストによって試した。
徳川家康が儒教(それも朱子学)を奨励したのは明智光秀の再来を防ぐためであった。しかしそのことが幕末の倒幕・王政復古の理論的根拠を提供することになった。天皇こそが王者であり、徳川家は覇者に過ぎないということだ。
中国人や朝鮮人は中華思想の徒である上に、儒教というまったく批判を受け付けない宗教に毒されているため、靖国神社に対する日本人の思いを理解できない。
マックス・ウェーバー(ドイツの社会学者・経済学者)は、「良い品質をもたらす仕事は成果主義の報酬だけでは生み出せず、来世を否定する儒教では仕事に打ち込もうとする精神を生み出せない」と語った。