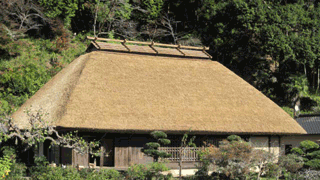男性的日本人へ
(日下公人)
「決断の前に決意をしておけ。決意するには理由が必要だが、決断に理由は不要。ただタイミングをみるだけだからだ。」(羽野水産会長:羽野重雄)
決断力が不足している者は、普段から英知の蓄積が不足している。
学校で教える理論では、何時が「好機」なのかを教えないから、会議をすれば慎重論者が必ず勝ち、そのせいで好機を逸してしまう。男の本領は踏み込んで機をつかむことだ。
日本は崩壊などしていない。そう思うのは新聞・テレビ・週刊誌の読み過ぎだ。確かに崩壊現象もあるが創造現象もあって、不動の基盤も頑然とあるのだ。これからの日本は「質の創造」で世界に貢献するため、破壊と創造が進行しているのだ。
日本は資本主義より人本主義で行け。
企業価値には3種類ある。株主にとっての価値。従業員や取引先にとっての価値。社会にとっての価値。しかし法律では会社は株主のものとしている。ここに問題を生ずる根源がある。
これからの日本の産業は、アイデア・センス・工夫・努力が物をいう。
グローバルスタンダードとは新入りが既成の共同体に入れてもらいたいため、高飛車に言っているもの。郷に入りては郷に従えの反対なので嫌われる。歴史の浅いアメリカではこの手の揉め事が多くすぐに裁判へ持ち込む。しかしようやく裁判の不毛さに気付き始めた。日本では昔から話し合いというローカルスタンダードで折り合いをつけてきた。というより日本の法律は対外的な建前に過ぎない。日本がアメリカ化しているのも事実だが、実はアメリカも日本化している。
日本のビジネスマンはアメリカ企業と取引するに当たって明確に意思表示をするようになった。しかしアメリカ風の取引を良いとは思わないので、こちらが優位に立っている相手に対しては日本風を押し付ける。すると相手が合わせてくる。しかし官界・学界の人間はこれをしようとはしない。
日本風のビジネスをやる会社はアメリカでも繁栄している。しかしそうしない会社は共食い競争をしている。ヨーロッパ企業もアメリカへの投資を減らし、ドルも持たなくなる。それでアメリカは金詰りになってヨーロッパ資産を売却して持ち帰る。金詰りはますます昂じて金利も上がって苦しくなる。そうなるのは真面目な取引をしないからだ。常に相手を騙そうとしているから世界中が寄り付かなくなる。ところで日本風の「無邪気・あどけない・かわいい」という文化がマンガやアニメを通じて世界中の子供達に浸透している。彼らが大人になる頃には日本風が定着しているだろう。かくして世界は日本化する。
日本では権利を主張しなくても相手にそれを察する義務がある。しかしアメリカでは権利を主張しなければ誰も認めてくれない。お互い権利を主張するから訴訟合戦になる。そのため法と理屈を覚える。感情的になると理屈では勝てないからだと思われるので、冷静に理詰めでやる。つまり権利は客観的に存在するものであり、それを証明することは可能であるという前提で進められる。逆に日本では感情的になった方が勝つ(笑)。
世界的に見て日本ほど魅力溢れる国はない。だから企業進出する際も相手国にあつかましいほどの条件を突きつけても大概断られない。