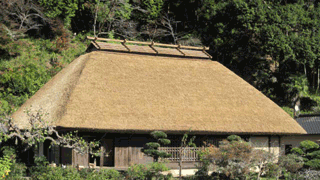仏教
仏教は日本に入ってきた後、ビーフカレー仏教となった。
古代インド思想の特徴は生きることを苦しみと捉えたこと。虚無主義・快楽主義・唯物主義・苦行主義・決定論・懐疑論などの思想が生まれた。
唯物思想は精神などというあやふやなものはなく、物質があるにすぎないとするもので、後世マルクスも資本論の中でそう唱えた。
仏教では輪廻転生を説くが、この思想は以前からインドにあったもの。人間は永遠に死なず、現世での行いによって来世は六道の中のどれかに生まれ変わるという考え。
キリスト教では、人々を死の不安から救うために「最後の審判」というものを考え出し、それまで人間は死んだのではなく眠っているだけで、その時が来たら起こされて審判を受け、最終的に運命が決定すると説く。だから火葬せずに土葬をしてできるだけ肉体を残そうとする。
キリスト教では永遠の命を求めるが、仏教では逆に生きることから永遠に解放されたいと望んだ。生きることは苦しみであり、永遠に続く輪廻転生の輪から抜け出すにはどうすればいいのかを考えた。悟りを開いて抜け出すことを解脱といい、解脱すると転生せず死ねる。そのために修行している者を菩薩といい、解脱した者を仏陀あるいは如来と呼ぶ。ブッダは音訳、如来は意訳である。
南無とは「あなたに帰依します」という意味。
鎌倉時代に様々な新興仏教が生まれた。日蓮宗もその一つだが、他の宗派と違うのは日蓮という僧の名前が付いていること。他にそんな例はない。日蓮は法華経が唯一最高の経典であり、その教えが真の仏教であるとし、他の宗派はすべて誤りだとした。日蓮は「念仏無間」「禅天魔」「真言亡国」「律国賊」と言っている。それはキリスト教のように異端を認めない厳しい宗教であった。ところで法華経の中には悟りを開く方法については書かれておらず、書かれているのはいずれ法華経の聖者である上行菩薩がこの世に生まれ、教えを広めるということだけである。そこで日蓮は自らを上行菩薩であると信じた。そのために日蓮自身が信仰の対象となり宗派に彼の名前がついた。しかし他宗派は彼を菩薩として崇拝するなどとんでもないとして迫害した。
神道
もともと神道は多神教であるが、キリスト教に対抗するため無理矢理一神教的に強化したものが「国家神道」である。そのため一神教の影響をものすごく受けている。国家神道はとても愛国主義的・排他的・独善的である。もしキリスト教国に占領されてしまえば、古来の伝統文化も破壊されて南米のように奴隷になってしまう危険性があったからだ。そのため神仏分離令を出し、神社をすべて国家の統制下に置き、国家機関として神を祭る地位のトップに天皇を据えた。これはローマ法王に対抗するためである。
神道は邪神をも祭りなだめることで善神に変化させようとする。そのため神道は徹底した性善説に基づいていると言っても良い。
卑弥呼は名前ではなく称号である。「日の巫女」の意味だろう。言霊信仰により使者が女王の本名を明かすはずがなく、「ヒミコ」と称号で答えたので中国側が名前と思い込み、他民族を蔑む習慣から卑賤な字を当てたものである。
怨みを作らないことが神道では最重要課題である。
日本の歴史学者は日本が無宗教であるという前提に立って分析・解釈している。
戦国時代にキリスト教が伝来し布教されたが広まらなかったのは、幕府による禁教令が出たこともあるが、それ以上に日本人の中に一神教の原理を受容できない素養があったからである。
明治維新以降、国家神道が形成される中で国家に属さない独自の神道を目指す公認された団体があった。それを「教派神道」と言う。黒住教、天理教、金光教などがある。しかし国家神道に逆らう大本教だけは厳しく弾圧された。
日清・日露戦争は決して侵略戦争ではないし、大東亜戦争も自衛戦争であった。日露戦争の勝利によってアジア人が初めて白人キリスト教帝国を打ち破ったことが、その後のアジア諸国独立の道を開いた。
靖国とは「国を守る」という意味。全国の護国神社の頂点に靖国神社がある。戦いの中で国家のために死んだ人達を天皇・国家の名において祭っている。